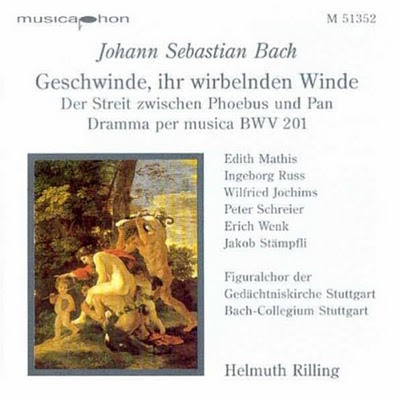メルヘンとファンタジーの魅力作
バロックの巨匠ヘンデルの作品から声楽やオペラを無くしてしまったら、どうなるのでしょうか……。?それはヘンデルの作品の宝のほとんどを失うことになるでしょう。それほどヘンデルの声楽やオペラは他に代え難い魅力があるのです。たとえばイエス・キリストの人物像を描いたオラトリオ「メサイア」を最初から最後まで胸をワクワクさせながら聴かせられる作曲家が他にいるでしょうか?
他の作曲家の作品からの引用が多いとか、旋律があまりにも単純だとか非難されることが多いヘンデルですが、それにしても出来上がった作品のひとつひとつは完全にヘンデルの音楽として血肉化されているのです。
この「エイシスとガラテア」もそうで、後年の「サウル」「テオドーラ」「エフタ」のように骨太で深刻な内容ではなく、メルヘンとファンタジーに富んだ魅力的な音楽劇なのです。また全曲を聴き通しても80分程度の比較的短いこの作品は表現にまったく無駄がなく、もっともっと愛されてもいい音楽だと思います。
ストーリーは羊飼いの若者エイシスとニンフ(精霊)の娘ガラテアは仲のいい恋人同士です。怪物ポリフェーマスがエイシスに嫉妬し、岩を投げつけて殺してしまいます。しかし、その後エイシスはガラテアの力により涸れない泉となって永遠の命を得ます。実に単純なお話ですが、ここに現れる牧歌的な舞台背景や愛の教訓、さまざまな比喩は物語を意味深く魅力的に演出しているのです。無邪気なメロディや懐かしい響きも顔を覗かせて、最後まで飽きることがありません。モーツァルトが愛すべきヘンデルのこの作品を編曲したのもわかるような気がします。
この曲を聴くと、とても晴れやかな明るい気分になります。心のもやもやを洗い流すかのように暗い影を消し去ってくれるからです。ヘンデルの純粋無垢な旋律だとかメルヘン的なテーマは中身が薄いのでは?と思われがちですが、決してそんなことはありません。ヘンデルの紡ぎ出すメロディは人の心の奥底にある希望や愛の扉を巧みに開けてくれるのです。
この曲はモーツァルトが編曲した版を使用したトレヴァー・ピノックの演奏が最高です。とにかく前進するエネルギーに溢れ、さわやかな空気感や牧歌的な雰囲気を見事に表出しています。歌手陣も素晴らしく、ボニーの真っ直ぐで理知的な声がガラテアにぴったりだし、マクドゥガルの端正な美声もエイシスにはまっています。残念ながらこの録音も今や廃盤の憂き目にあっています(iTunesストアではダウンロード可能)。ただただ、復活を願ってやみません。