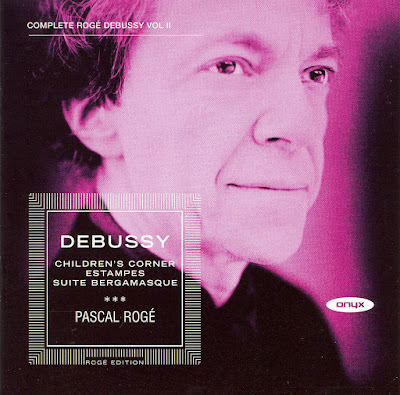子供たちのピュアな感性と
大人が見つめる温かな眼差しが
融合された音楽
大人が見つめる温かな眼差しが
融合された音楽
ドビュッシーの作品としては比較的親しみやすく、人気が高いのが『子供の領分』です。
タイトルから想像できるように、子供たちのピュアな感性をテーマにしているのですが、大人が見つめる温かな眼差しがそこにプラスされていて、極めて詩情豊かな作品として仕上がっているのです。
これはドビュッシーの卓越した感性だからこそ作り得た作品でしょうし、その創造性に富んだユニークな音楽は大人が愛する子供に聴かせる音楽絵本と言ってもいいでしょう。
実はこの作品、ドビュッシーが初めて授かった娘(長女クロード・エマ)への想いを込めて書かれているのです。
日常の光景が
美しく変貌する瞬間
美しく変貌する瞬間
まず、前奏なしでいきなり主題が開始される第1曲 「グラドゥス・アド・パルナッスム博士」は何と上機嫌でユーモアたっぷりなのでしょう! もちろん音楽は楽しいだけではありません。生き生きとしていて、曲が進むと美しい表情が次々と紡ぎ出されていきます。特に中間部の虹を想わせる音色は日常の光景が美しい輝きを放っていくかのようです。
おどけたリズムとテーマの「象の子守歌」も童心を呼び覚ますのに充分ですし。可愛らしい音色が夢の世界を描き出す「人形ヘのセレナーデ」も絶品です。どなたもよくご存知「ゴリウォーグのケークウォーク」はどういうわけかテレビで使用されるときは「ジャポニズム」を扱ったり、「浮世絵と印象派」のようなアートと日本との接点を匂わせる趣旨の番組が多いのは何故なのでしょうか? たぶん、それだけ曲が異国情緒にあふれており、様式に固執しないドビュッシーの才気があふれているからなのかもしれません。
しかし、この作品をより魅力的にしているのは第4曲の「雪は踊っている」と第5曲の「小さな羊飼い」でしょう。「雪は踊っている」は窓辺で降りしきる雪をじっとみつめている子供たちの様子を描いているのですが、雪が舞う動的なリズムとテーマが印象的です。次第に振り続ける雪は雪の精へと変貌し幻想的な雰囲気であたりを覆っていくのです。
「小さな羊飼い」は幼い胸に秘められた短い詩のようです。切々と弾かれるピアノの陰影や1小節ごとの間合いが何ともいえない情感を醸しだし、愛おしさや懐かしさがじんわりと漂っていきます。
ハイドシェックとベロフ
クリエイティブな名演
クリエイティブな名演
このピアノ曲は曲の性質上、演奏には少なからず夢を膨らます詩情豊かな感性や創造性が要求されます。たとえどんなにテクニックが優れ、演奏が立派でも四角四面の解釈はつまらないし、似合わないのです。
その点で優れているのはエリック・ハイドシェックとミシェル・ベロフでしょう。
ハイドシェックとベロフに共通するのはとことん音楽を愛し、愉しんで弾いてるところですね。
その点で優れているのはエリック・ハイドシェックとミシェル・ベロフでしょう。
ハイドシェックとベロフに共通するのはとことん音楽を愛し、愉しんで弾いてるところですね。
ハイドシェック(キングレコード)の演奏は型にはまらない変幻自在なスタイルをとっているのですが、音色に柔らかさがあるのと音符の読みが深いため、各曲ともに新鮮な驚きと感動があります。聴く人の心に発見や様々なイメージを呼び起こす魔法のような名演奏と言えるかもしれません。
ベロフの演奏(DENON)は音色が豊かで、リズムは弾み、造型はキリッとしていて、フレージングも自然! どこをとっても音楽性満点で、特別なことはしていないはずなのにドビュッシーを聴く喜ぶを最大限に与えてくれます。最初に「子供の領分」を聴くならベロフは絶対的にお勧めですね!