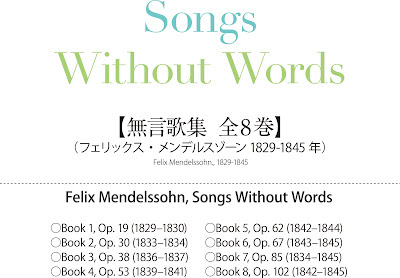オラトリオ「エリヤ」の聴き比べ
メンデルスゾーンの傑作といえば、私が真っ先に思い浮かべるのが、オラトリオ「エリヤ」です。
オラトリオという響きから「難しい作品なのでは…」と敬遠されるかたも少なくないと思いますが、いえいえ、決してそんなことはありませんよ!
この作品の魅力を一言でいえば親しみやすく、口ずさみやすいアリアや合唱曲がたくさん散りばめられていることです。しかもエンディングに向かって曲は大いに盛り上がり、圧倒的な感動を共有できるところも大きな魅力なのです。オラトリオの入門曲としても「エリヤ」は間違いなくお勧めですね!
「エリヤ」はドラマチックな曲想、崇高な祈りの感情、甘美なメロディ等々、メンデルスゾーンの音楽の魅力が余すところなく発揮された傑作中の傑作なのです。
「エリヤ」はドラマチックな曲想、崇高な祈りの感情、甘美なメロディ等々、メンデルスゾーンの音楽の魅力が余すところなく発揮された傑作中の傑作なのです。
現在のところ、アルバムも数多く出ていますし、新譜も続々と出てきていますね!
さて、今回は私がこれまでに聴いてきたエリヤのCDの中から特に印象に残ったアルバムをいくつかご紹介しましょう。
モダン楽器演奏の双璧
サヴァリッシュ盤とリリング盤
まず、最初に挙げたいのがヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団およびライプツィヒ放送合唱団、エリー・アメリンク(ソプラノ)、ペーター・シュライヤー(テノール)、テオ・アダム〔バス)他(フィリップス)です。
録音が1968年と古いのが難点と言えば難点ですが、演奏は全体的に表情の振り幅が大きく、オペラのようなドラマチックな緊張感と宗教的な情感が一体となった響きがこの作品にピッタリです。
曲の本質を突いたサヴァリッシュの解釈や、アダムやシュライヤーら名歌手たちの強い印象を残す歌唱は今もって最高ですし、確固とした信念に基づく合唱も素晴らしいの一言に尽きます! かつて「エリヤ」といえば、このサヴァリッシュ盤がファーストチョイスでした。
続いてヘルムート・リリング指揮シュトゥットガルト・バッハ・コレギウムおよびシュトゥットガルト・ゲヒンゲン聖歌隊、クリスティーネ・シェーファー(ソプラノ)、カリッシュ(テノール)、シャーデ(テノール)他(ヘンスラー)もなかなかの名演です。
サヴァリッシュ盤に比べるとあっさりした印象も受けますが、シェーファーを始めとするソリストたちがメンデルスゾーンの音楽の叙情性を自然な語り口で聴かせてくれるため、身構えずに音楽に浸かれるのがうれしいところです。リリングの指揮も堅実でありながら、本質をしっかりと捉えており、エリヤの作品としての素晴らしさが歪みなくストレートに伝わってくる感じです。
クルト・マズア指揮ライプツィヒ放送管弦楽団〔フィリップス)やミシェル・コルボ指揮リスボン・ グルベンキアン管弦楽団、合唱団〔エラート)も素晴らしいところがたくさんありますが、全体を通した感銘では前記2盤にやや劣るかもしれません。
21世紀の最高の名演
ベルニウス盤
トーマス・ヘンゲルブロック(指揮)バルタザール・ノイマン・アンサンブル&合唱団、ゲーニア・キューマイアー(ソプラノ)、アン・ハレンベリ(アルト)、ローター・オディニウス(テノール)(ソニーミュージック)はオリジナル楽器を使用した演奏ですが、決して薄味な響きになることなく、エネルギッシュで気迫に溢れた素晴らしい演奏を繰り広げています。楽器の音色や表情の彫りが深く、ストーリーを彷彿とさせる豊かな雰囲気を創りあげているのです! 特に合唱は指揮者の音楽作りに強く応答していて、曲想によっては陰影に満ちたドラマチックな表情や息吹が伝わってきます。
フリーダ・ベルニウス指揮シュトゥットガルト・クラシック・フィル、シュトゥットガルト室内合唱団、レティツィア・シェレール(ソプラノ)、サラ・ウェゲナー(ソプラノ)、ルネ・モロク(アルト)、ヴェルナー・ギューラ(テノール)他(Carus)は一度聴いただけだと個性が乏しいように感じるかもしれませんし、薄味な表現に思われても決して不思議ではありません。しかし何度聴いても飽きない、味わい深い名演奏といっていいでしょう。
合唱のスペシャリストとして名高いベルニウスの手腕はここでも冴えに冴えています。特に合唱の各パートは発声に曖昧模糊とした欠点がなく、終始、澄んだ美しいハーモニーを表出しているのです。しかもその音楽性の高さや静かさの中に漂う無限のニュアンスといったら……。聴きなれたはずの数々のナンバーからひたすら豊かで滋味あふれる音楽が泉のように湧き出してくるのです!
もちろんソリストたちも奇をてらわず、素直に心を通わせる歌唱がとても心地よく感じます。とにかく勢いや力任せになりやすいこの作品を、決して無理せず、自信とゆとりに満ちた表現を貫いているところは見事というほかありません。作品への深い解釈に裏付けられたオリジナリティとそれに見合うスキルや愛情を持って演奏するとこのような名演が誕生するといういい見本でしょう。