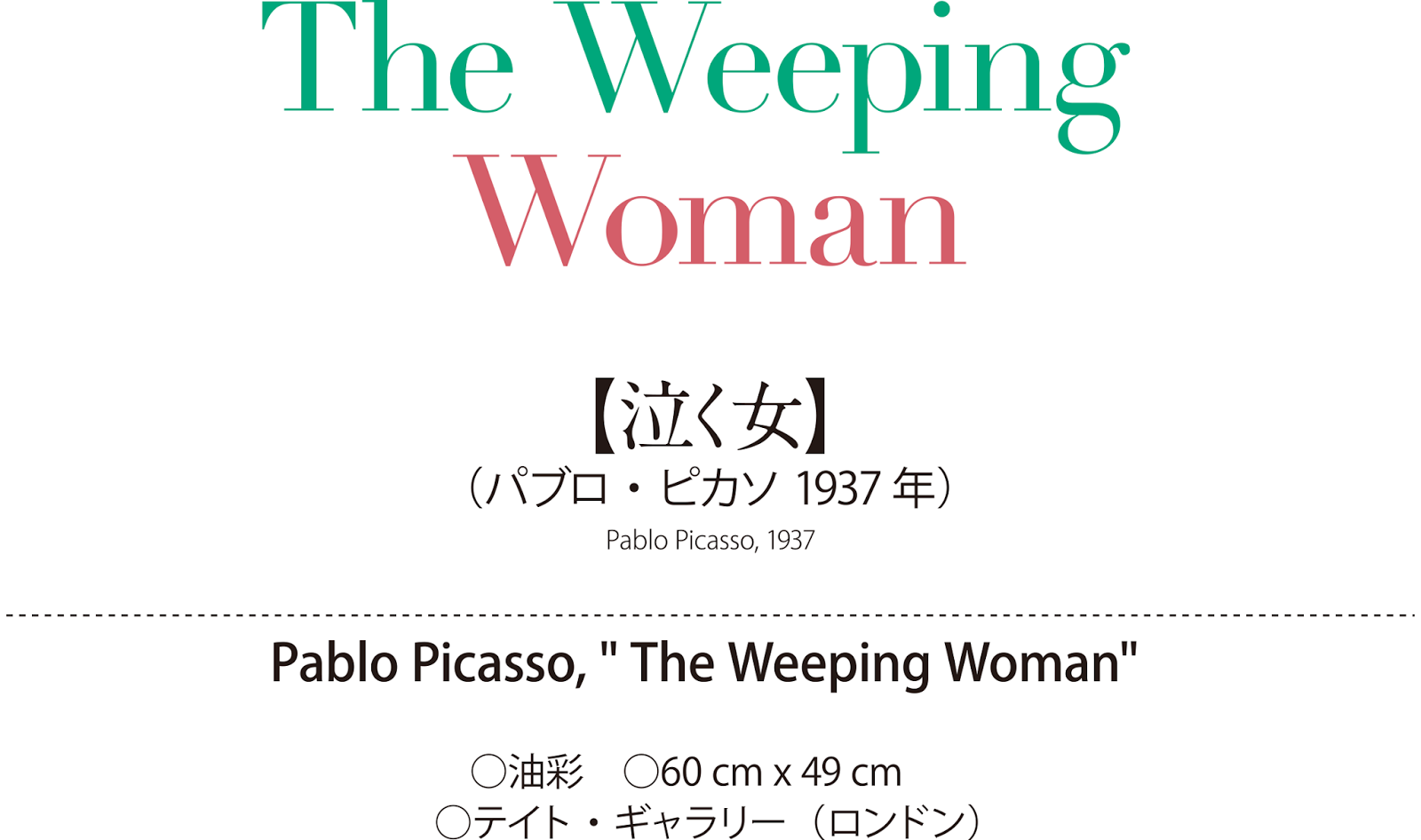「キチッと正装したフォーマルスタイル」の
モーツァルトの交響曲
モーツァルトにとって交響曲は彼の作品の中でどのような位置づけだったのでしょうか? ベートーヴェンの場合だったら交響曲は最重要なジャンルと考えて間違いありません。第3「英雄」、第5「運命」、第6「田園」、第9のような歴史的傑作をはじめとして、彼が作曲した9つの交響曲は西洋音楽史を語る上で絶対に外せない交響曲ばかりですね!
モーツァルトの交響曲は全部で41曲と言われています。この中には初期のセレナーデのようなあっさりとした形式の物もあれば、後年の形式・内容ともに充実した作品に至るまで様々です。ただし、よく知られた交響曲となると25番、29番、35番、36番、38番、39番、40番、41番あたりに限定されることでしょう。それ以外の作品は演奏会で採りあげられることも稀ですし、知っている人も少ないのではないでしょうか……。
また、モーツァルトファンの中には「彼の音楽の真骨頂はオペラだよ」とおっしゃる方も少なくありません。確かに『フィガロの結婚』、『魔笛』、『ドン・ジョバンニ』、『コジ・ファン・トゥッテ』等の人物描写は卓越していますし、まるで劇中から登場人物が抜け出してきそうな音楽的な魅力とリアリティに溢れています。それはモーツァルトのインスピレーションが冴えに冴え、生き生きとした感性が縦横無尽に発揮されているからなのでしょう。
それではモーツァルトの交響曲の魅力とは何でしょうか?
以前このブログで「彼の交響曲はプライベートなカジュアルスタイルではなく、キチッと正装したフォーマルスタイル」と表現したことがありました。モーツァルトにとって交響曲とはオペラや協奏曲、管弦楽曲とは少々違った特別な領域だったのです。それはザルツブルクやウィーンの聴衆に向けて正統的な作品を作ろうという意識の表れだったのかもしれません。
とは言うものの、晩年の交響曲はモーツァルトが本当に書きたい音楽だけを書いたと言ってもいいでしょう。特に40番ト短調と41番「ジュピター」は天才的な技巧・音楽性が高い芸術性と結びついて誕生した空前の傑作です!
41番「ジュピター」が作られた頃はモーツァルトが生涯で最も辛く苦しい時代だったとも言われています。しかし音楽の完成度、精神性の高さはそんなことを一変に忘れさせてしまうのです。
屈強で揺るぎない第1楽章
天上の調べを映すフィナーレ
この交響曲の偉大なところは、まず第1に内容がはち切れんばかりに盛り沢山なのにもかかわらず、音楽の流れが遮断されることなく展開され、しかも造形が一切崩れていないことでしょう! そして第2にどこもかしこも澄み切った精神や深い人生の意味が音楽として表現されていることですね。一音一音の持つ意味が非常に神秘的で深いです!第4楽章のフーガを「奇跡だ」という音楽学者の方は大勢いらっしゃいますが、この交響曲はすべての楽章が奇跡だと評してもおかしくないくらいです!
たとえば、第一楽章の印象的な三連打のリズムで開始される第一主題ですが、何と堂々とした足どりと確信に満ちたテーマでしょうか! しかも屈強で揺るぎない前進する力に溢れたこの楽章は悲しみや苦悩といったさまざまな人間感情と共存しながら、それらを受け容れる大きな度量も備えているのです!
第2楽章アンダンテは歌うような旋律を基調としています。しかし、その彩りは大変に翳りが濃く、人生の秋がひたひたと伝わってくるようです。
第3楽章メヌエットは非常にシンプルで大胆な和声によって構成されています。第4楽章へと続く重要な橋渡し的役割を果たす楽章ですが、もちろんそれだけではありません。緊張感に満ち、充分に力強く宇宙的な拡がりを持った主題が印象的ですね。
第4楽章フィナーレは間然すべきところがない驚くべき音楽です!まるで宇宙意志に貫かれているのでは……と思うくらい、対位法の素晴らしさや主題の展開と発展が音楽に広々とした空間を生み出していきます! 特に中間部で弦楽器とオーボエ、クラリネット、ホルンらが交わす付点のリズムと下降音型によって生まれるその独特の空間の拡がりは天上の調べを感じますね。ここは音階のリズムやバランスがちょっとでも崩れると奇妙な音楽になってしまう危険性をはらんでいるので、よほどモーツァルトの精神と肉体は研ぎ澄まされた高い境地にあったのでしょう!
圧倒的な感動を約束してくれる
カザルスが遺した名演奏!
第4楽章の奇跡のフーガ、第1楽章の引き締まった造形、第3楽章の形而上的なメヌエットとくれば、ともすれば形の立派さだけが鼻についてしまうのがこの交響曲演奏の最大の盲点であり難しさでしょう。ワルター、トスカニーニ、クレンペラー、カラヤン、バーンスタイン、クーベリック、最近ではラトル、ブリュッヘン、アーノンクール、インマゼールらの素晴らしい演奏がありますが、でもこれらが絶対か……と言われれば何かもう一つ食い足りない感じがして仕方ないのです。
しかしこの作品から深い意味と感動を伝えてくれる演奏もあることはあります。その代表格が
パブロ・カザルス=マールボロ祝祭管弦楽団のライブ演奏です。カザルスの演奏は温かな人間味を感じさせ、モーツァルトが伝えたかったメッセージがどの楽章からもひしひしと伝わってくるのです。
「ジュピター」では出だしから気迫みなぎる音に圧倒されます。第1楽章の怒涛のように押し寄せる感情の波は苦しみを乗り越えるべく必死にあえでいるかのようですし、第2楽章の深い呼吸で奏されるカンタビーレは魂の鎮魂歌のような趣さえも湛えていきます。第3楽章の緊張感と自在感に満ちた表現や第4楽章のなりふり構わず前進する演奏の凄さ。これはカザルスが残したベストパフォーマンスの一つと言えるでしょう!
カール・シューリヒト指揮パリオペラ座管弦楽団の演奏は個性的で、第1楽章のテンポは早すぎるほどですし、せかせかした感じが否めません。しかし、第4楽章フィナーレの翳りの濃い響きはとても味わい深く、壮麗な「ジュピター」の別の魅力を教えてくれた忘れ難い演奏です。