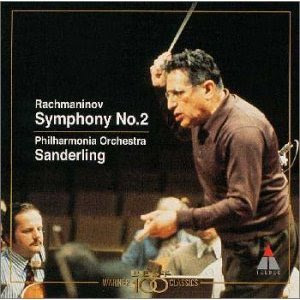底抜けに明るく、輝かしく若々しいスピリット
皆さん、モーツァルトの交響曲として、真っ先に思い出される作品といえば何が浮かんできますか?おそらく多くの方は40番、41番「ジュピター」、25番あたりを挙げられることでしょう。逆に曲は有名だけれど、あまり印象に残らない曲といえば、意外と多くの方が交響曲35番「ハフナー」あたりを挙げられるのではないでしょうか。
ハフナーは全体的に短い曲ですし、性格自体も祝典的な音楽のようで、今ひとつ心に深く沁みる…。というのとは違うようです。でも、底抜けに明るく、輝かしく若々しいスピリットを感じさせるこの作品は、いつでも悩める人に微笑みかけてくれる魅力作なのです。しかも、この曲はいくらでもデフォルメ可能ですし、聴く人を絶えず驚かせ、楽しませてくれる予感が期待できる音楽なのです。
この曲には忘れられない演奏があります。カール・シューリヒトが1956年(ステレオ最初期)にウィーンフィルを指揮したものがそれです。大学生だった私は、バーンスタインの「リンツ」がいいという評判を聞きつけ、ぜひ聴いてみたいと思いカセットテープを購入しました。そのバーンスタインの「リンツ」のB面に入っていたのが
シューリヒトの「ハフナー」だったのです。
忘れられないシューリヒトの演奏
当時、
シューリヒトの「ハフナー」はバーンスタインの演奏の付録くらいにしか考えていませんでした。最初に聴いたバーンスタインの演奏は案の定素晴らしく、メリハリが利き情感豊かな本当に魅力的な演奏でした。
では、シューリヒトの「ハフナー」はどうかというと、第一楽章の最初から楽器のアンサンブルが微妙にずれ、「これって本当にスタジオ録音なの?」と思うくらい自由奔放で即興的な雰囲気に満ち満ちたものだったのです。しかし、曲が次第に盛り上がるにしたがって、楽器の響きは生き物のように多彩な表情を生み出し、刻々と表情が変化し、さまざまなニュアンスを高い芸術性と共に伝えてくれたのです。それはこれまでに聴いたことのない高い演奏芸術の究極的な姿のひとつでした。音楽を聴く喜びを素直に教え、再認識させてくれたのがこのシューリヒトの演奏だったのです。
それからしばらくの間はすっかりシューリヒトの芸術の虜になり、彼の残したモーツァルト、ハイドン、シューマン、ベートーヴェン、ブルックナー等の演奏を次々と聴きました。息もつかせぬ表現をあっさりとやり遂げてしまうシューリヒトの凄さにしばらくの間、舌を巻き、大いに感動したものでした。